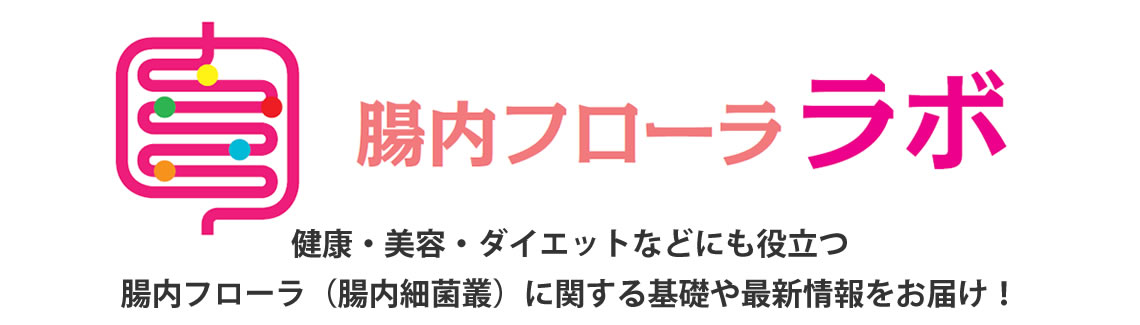こんにちは!
いつも弊社のメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
オーエム・エックスの社長の高畑宗明(農学博士)です。
6月になり、梅雨の季節がやってきました。『OM-X』を製造している
(株)バイオバンクでは、毎年1回、世界中のOM-X販売代理店の方々を
集めて世界会議を開催しています。最新の研究情報や、各国のサプリメン
ト市場や医療情報を共有し、知識の向上と親睦を深めています。今年は今
月8日からアメリカに渡り、私は『OM-X』の免疫賦活作用やアレルギー抑
制作用などの研究データを発表します。免疫についてのデータは、9月に
学会発表、その後の論文投稿を予定しています。発表ができたら、みなさ
まにも後日お知らせいたします。
さて、梅雨の季節に世間でよく話題になるのが「カビ」ですね。「カビ」
と聞くと、なんだか汚くて色々な病気の原因になりそうというイメージを
お持ちだと思います。もちろん、そのような病気や汚染の原因となる「カ
ビ」もいるのですが、実は私たちの生活に欠かせないお酒、味噌、醤油、
チーズなどを作る過程で役に立っている「カビ」の方が多いのです。今話
題の「麹菌」も「カビ」の仲間なのです。
==================================
![]()
![]() 第20回 『日本の発酵食品に使う「麹菌」は「カビ」の仲間!?』
第20回 『日本の発酵食品に使う「麹菌」は「カビ」の仲間!?』 ![]()
![]()
==================================
![]() 「カビ」は現在80,000種類以上確認されています
「カビ」は現在80,000種類以上確認されています
微生物とは「肉眼では識別できないくらい小さな生き物」という定義があ
てはまります。ただし、微生物と一言で言ってもその種類は多様です。微
生物には「細菌」「放線菌」「ラン藻」「古細菌」「菌類」「藻類」「原
生生物」などが含まれます。その中でも、遺伝情報を持つDNAが核膜とい
う膜に包まれているものを「真核生物」、核膜がない微生物を「原核生
物」と呼んでいます。微生物を分類すると、下記のようになります。私た
ち人間は「真核生物」ですので、核膜のありなしで分ける分類は、微生物
に限ったものではありません。
原核生物:「細菌」「放線菌」「ラン藻」「古細菌」
真核生物:「菌類」「藻類」「原生生物」
今回のテーマは「カビ」についてです。上の分類の中で、「カビ」は「菌
類」に属します。「菌類」には他にも「酵母」や「キノコ」が含まれます。
「キノコ」や「酵母」と「カビ」が同じ種類というのも驚きですよね。細
かく言うと「カビ」と「キノコ」は菌糸を出し、「酵母」は菌糸を出さず
分裂や出芽という方法で増殖するといった違いがあります。でも、みなさ
んがよくご存知の「乳酸菌」や「ビフィズス菌」、「納豆菌」といった菌
は「細菌類」ですので、「カビ」とは違う種類の微生物に分類されている
のです。そして、この「カビ」の中にも種類が豊富に存在し、現在なんと
80,000種類以上も確認されています。
![]() 「カビ」はどんなところに生えやすいの?
「カビ」はどんなところに生えやすいの?
「カビ」は生殖活動のために必要な「胞子」と呼ばれる細胞を作ります。
この「胞子」は空気中をフワフワ浮遊して室内の表面に付着します。温度
が5℃~35℃前後であれば、「カビ」は家の建材や表面のホコリや汚れ、
さらにはそこにある水分を栄養にして生育することができるのです。一般
住宅の室内平均温度は10℃~30℃とされていますし、空気中にはいつも
一定量の湿度があります。そのため、「カビ」は一年中発生可能な状況に
あります。
一般的に「カビ」が生育するためには、80%以上の湿度が必要です。浴室で
は湿度が高く、80%を超えることがしばしばありますが、他の部屋の湿
度が80%を超えることはそれほど多くありません。なのに、部屋の中に
「カビ」が生えてしまうことがあります。この理由は、「カビ」が生育に
使用するのは空気中の水蒸気ではなく、部屋の表面の水分だからです。部
屋全体の湿度が低めの場合でも、壁や窓の表面に水分が多く存在している
場合、そこは「カビ」にとって好条件な環境となります。部屋の中にはお
よそ空気1立方メートルあたり数個から数千個の「カビ」が浮遊していま
す。さらに、ホコリ1gあたりには10万個から100万個の「カビ」が検
出されます。空気の入れ替えや、ホコリの除去は「カビ」を定着させない
ためにも大切なことなのです。
もし壁や窓に結露が発生した場合、まず結露をよく拭き取りましょう。ま
た通気性の確保も心がけるべきことです。表面に付着している汚れも「カ
ビ」にとってよい栄養源となりますので、きちんと汚れは拭き取りましょ
う。「カビ」が生育してしまった後は、市販の漂白剤や「カビ」用消毒剤
を使って清掃します。
「カビ」が原因で発生する病気もあります。例えば、白癬菌症(水虫)の
原因になっているTrichophytonも「カビ」の仲間です。また、「カビ」
が作る「胞子」はシックハウス症候群、喘息などのアレルギー疾患の原因
になっている場合もあります。「カビ」が発生している資料や置物など取
り扱ったり掃除する場合には、マスクの着用をお薦めします。「カビ」の
中には毒素を作る種類のものもいますので、「カビ」が生えた食品は基本
的には口にしない方が無難です。しかし、全ての「カビ」が毒を作り出す
わけではありません。私たちは日常生活において、「カビ」を利用してい
る食品を常に口にしているのです。それは「発酵食品」です。
![]() 「麹菌」は実は「ニホンコウジカビ」という「カビ」の仲間
「麹菌」は実は「ニホンコウジカビ」という「カビ」の仲間
「カビ」は多くの酵素を分泌します。この酵素を利用して様々な食品に産
業的に用いられています。例えば、「カビ」が作るプロテアーゼを用いて、
食品のタンパク質をアミノ酸に分解することで風味を出しています。また、
デンプンの糖化にはアミラーゼが用いられています。チーズには「アオカ
ビ」を利用したロックフォールやゴルゴンゾーラなどのブルーチーズや、
「シロカビ」を用いたカマンベールなどがあります。
そして日本では、日本酒、焼酎、醤油、味噌などの発酵食品に、「ニホン
コウジカビ」という種類の「カビ」が利用されています。今、世間では
「麹(こうじ)」を用いた料理がブームとなっていますね。この「麹」を
作る際に使われる「麹菌」は実は日本特有の「カビ」の仲間なのです。
(ちなみに「麹」と「麹菌」は異なります。「麹」とはサツマイモ・麦・
米などの穀物に麹菌を混ぜあわせ「麹菌」を繁殖させたもの、「麹菌」と
は「麹」を作る時に使われる「カビ」の名前です。)
「麹菌(=ニホンコウジカビ)」はカビの仲間で、デンプン分解能力やタ
ンパク質分解能力に優れています。この役割を果たしているのが酵素です。
デンプンを分解するアミラーゼや、タンパク質を分解するプロテアーゼが
代表的な酵素で、その他にもペクチナーゼやタンナーゼ、セルラーゼ(繊
維質の分解に役立つ)を作り出しています。この中でもアミラーゼは現在、
医薬品「タカジアスターゼ」として消化薬として医薬品に配合されていま
す。
日本酒製造に用いられる「麹菌」は、米のデンプンを分解する必要がある
ために、アミラーゼを多く含むものが利用されます。一方、味噌や醤油の
製造用には大豆のタンパク質を分解するためにプロテアーゼが多い「麹
菌」が利用されています。日本酒では、アミラーゼで分解されたデンプン
がブドウ糖になり、ブドウ糖が次の段階で「酵母」のエサとなってアルコ
ール発酵が行われます。こうして「麹菌」と「酵母」の働きによってアル
コール成分が作り出されお酒が出来上がります。また、味噌や醤油では、
「麹菌」のプロテアーゼで分解されたアミノ酸が、独特の旨味成分となっ
ています。もちろん「酵母」や「乳酸菌」も関わって、香りや色、甘味成
分作りに役立っています。この「麹菌」や「酵母」「乳酸菌」も地域によ
って微妙に種類が異なり、この多様性がその地域ごとに受け継がれる伝統
的な発酵食品の味や風味に反映されているのです。
実は「麹菌」は『国菌』に認定されています。2004年に東北大学名誉教
授の一島英治氏が日本醸造協会誌に「麹菌は国菌である」と提唱しました。
その後、2006年10月12日に日本醸造学会大会で「麹菌(正式名称=
Aspergillus
oryzae)」が国菌に認定されたのです。現在この菌は遺伝子
解析も進められ、多くの研究者がその機能性を探索し続けています。弊社
の『OM-X』に用いられている「TH10乳酸菌」も、タンパク質分解能力が
非常に高く、その他にも免疫賦活化作用や抗菌物質の合成など、多くの研
究成果が発表されている素晴らしい菌です。また、現在私たちはさらなる
機能性を持っている微生物の探索を続けています。微生物と言っても、本
当に多くの種類が存在し、私たちにとって悪さをするものもいれば、良い
働きをしてくれる菌もたくさん存在します。良い面と悪い面をきちんと理
解することで、きちんと微生物と共存し、その恩恵を享受していきたいで
すね。